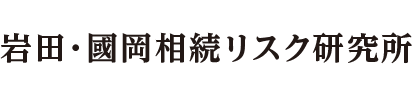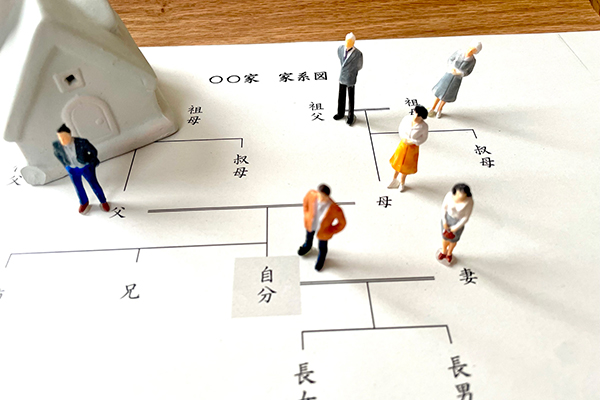相続エピソード
01.認知症になってからでは遅い!
家族信託で対策を
まだまだ元気と思っていても、一度認知症と診断されてしまうと、原則、預貯金を引き出したり金融商品や不動産を売買したりすることはできなくなり、事実上、資産は凍結状態になってしまいます。もちろん、母が所有している自宅を売却することも、賃貸などで活用することも困難になってしまいます。 医療の発達に伴い平均寿命は延びているため、まだまだ先のことと考えがちですが、日常生活に支障なく過ごせる「健康寿命」と、「平均寿命」とは異なります。 |
Aさんの母親のように入院を機にいっきに認知症が進んでしまう場合もあります。
その対策として考えたいのが、家族信託です。家族信託とは簡単に言えば、信頼できる家族に自分の財産を管理する権限を託す仕組みです。Aさんの場合、母親が元気なうちに、自宅の所有者である母を「委託者」、息子を「受託者」として契約すれば、息子の判断で家を処分したり活用したりすることができるのです。もちろん自宅の売却代金や賃貸としての収益は母親のものですから、母のために有効に使い、やがて母親が他界した後は息子が相続財産として取得することになります。
いずれ家族信託をと思いながら父も母もまだ元気だし・・・。そう考える方も多いでしょう。しかし認知症を発症してしまった後は、もういかなる契約もできません。不安や心配を感じたら、ぜひ考えてみたい家族信託です。
その対策として考えたいのが、家族信託です。家族信託とは簡単に言えば、信頼できる家族に自分の財産を管理する権限を託す仕組みです。Aさんの場合、母親が元気なうちに、自宅の所有者である母を「委託者」、息子を「受託者」として契約すれば、息子の判断で家を処分したり活用したりすることができるのです。もちろん自宅の売却代金や賃貸としての収益は母親のものですから、母のために有効に使い、やがて母親が他界した後は息子が相続財産として取得することになります。
いずれ家族信託をと思いながら父も母もまだ元気だし・・・。そう考える方も多いでしょう。しかし認知症を発症してしまった後は、もういかなる契約もできません。不安や心配を感じたら、ぜひ考えてみたい家族信託です。
02.事実婚の配偶者は?
その子供は相続人?相続の範囲とは
法律で定められた相続人のことを「法定相続人」といいますが、法定相続人になるには優先順位があります。 配偶者は必ず法定相続人となりますが、それ以外は(1)子ども、(2)親、(3)兄弟姉妹の順で、血のつながりが濃いほど優先的に相続できるようになっています。 |
配偶者に加え、一番優先順位の高い人しか相続人になれませんが、配偶者が亡くなっていたら、子のみ、親のみ、兄弟のみが法定相続人となります。しかし、配偶者の連れ子や子どもの配偶者は血縁関係がないので法定相続人になれません。愛人や内縁の妻(夫)も、法律上の夫婦ではないので法定相続人にはなれません。しかし養子や胎児(おなかのなかの赤ちゃん)、愛人の子も認知していれば法定相続人になれるのです。
血縁関係の有無が重要なファクターになる相続。いざというときのために、今一度相続の範囲、順位を確認しておいた方がよいかもしれません。
血縁関係の有無が重要なファクターになる相続。いざというときのために、今一度相続の範囲、順位を確認しておいた方がよいかもしれません。
03.遺言は、安心確実な法務局預かりの自筆証書遺言をすすめる。
自宅に住み続けたい長男が、長女と公平に分割するには「代償分割」、自分の財産から1000万円の代償金を長女に払う必要がありますが、長男はその代償金を用意することができませんでした。 それぞれが自宅の相続を主張し、仲良かったはずの姉弟に亀裂が生じました。 不動産は金融資産に比べて分割しにくいため、相続財産が不動産だけの場合、トラブルに発展するケースが多々あります。 |
こうしたトラブルを回避する手段が遺言書です。遺言書には大きく分けて公正証書遺言と自筆証書遺言の二つがありますが、公正遺言は財産額に応じ手数料がかかるなど敷居が高いのに対し、自筆遺言は、日付や名前、押印など書き方の不備から無効になる心配もあります。
そこでおすすめしたいのが、自筆証書遺言の保管制度。自筆遺言を法務局で預かる仕組みです。手数料は1通3900円。家庭裁判所の検認も不要。正しい形式で書かれているかどうか申請時に確認してくれるため、書式不備によるトラブルも避けられます。
相続人のなかに、介護に尽くしたり家業を手伝ったりしている人がいる場合もトラブルにつながりやすいため、後を継いでいく子どもたちのためにも、法務局預かりの自筆証書遺言を検討しましょう。
そこでおすすめしたいのが、自筆証書遺言の保管制度。自筆遺言を法務局で預かる仕組みです。手数料は1通3900円。家庭裁判所の検認も不要。正しい形式で書かれているかどうか申請時に確認してくれるため、書式不備によるトラブルも避けられます。
相続人のなかに、介護に尽くしたり家業を手伝ったりしている人がいる場合もトラブルにつながりやすいため、後を継いでいく子どもたちのためにも、法務局預かりの自筆証書遺言を検討しましょう。
04.アパート経営には手を出すな!
両親より継いだ土地を持つAさんは、土地活用を勧める業者の話にのり、更地にアパートを建てました。仮に空き室があっても30年間は一定水準の家賃収入があるとのことでしたので、将来的には家賃収入で娘の暮らしが楽になればと考えていました。しかし10年経過した際には条件の見直しがあり、修繕をしなければ家賃保証はなくなるといわれ、大規模な修繕費が必要になりました。 近くに新しいアパートができれば家賃も下げざるを得ず、娘の手に渡るまでには資産価値もなくなるのではと、頭を痛めています。 |
賃貸用アパートが建っている土地は相続税評価額が大幅に圧縮される小規模宅地等の特例もありますが、相続税を圧縮できても、そもそものアパート経営でマイナスが出れば意味はありません。
またBさんは、分譲時には高額だった中古物件を、今が買い時と勧められ購入。賃貸広告を見てみると、その物件が月20万で出ていましたし、相続税対策になるうえ、儲けも出ると考えていました。
しかし実際には20万では借り手がなく、一方で、相場より安く賃貸に出してはいけないという所有者間での申し合わせもあったのです。
高い利回りのある物件だといわれ購入したマンションですが、実は貸せない、売れない不良物件であることに後から気付きました。
高い投資利回りの根拠や、低リスクとなる条件の提案を目にすると心が揺れるものですが、不動産活用には落とし穴も多く潜んでいることを忘れてはいけません。
またBさんは、分譲時には高額だった中古物件を、今が買い時と勧められ購入。賃貸広告を見てみると、その物件が月20万で出ていましたし、相続税対策になるうえ、儲けも出ると考えていました。
しかし実際には20万では借り手がなく、一方で、相場より安く賃貸に出してはいけないという所有者間での申し合わせもあったのです。
高い利回りのある物件だといわれ購入したマンションですが、実は貸せない、売れない不良物件であることに後から気付きました。
高い投資利回りの根拠や、低リスクとなる条件の提案を目にすると心が揺れるものですが、不動産活用には落とし穴も多く潜んでいることを忘れてはいけません。
05.贈与するなら暦年贈与で「細かく長く」が、効果的
またBさんは、「住宅取得等資金の特例」を活用し、息子の住宅購入金として500万を贈与。しかし、通常の贈与とみなされ贈与税を払うことになりました。この特例の場合、年間110万円まで非課税の暦年贈与に加え、500万円までの贈与が非課税になりますが、非課税だから申告は不要と考え、申告をしていなかったのです。 |
贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までが申告期限であり、遅れての申告は課税対象になります。あとから気付いてももう取り返しはつかず…。
生前贈与を考えるなら長期計画で暦年贈与するのが効果的ですが、ここにも注意点があります。
Cさんは1人毎年110万までの贈与は非課税という暦年贈与の仕組みを利用し、子どもたちに毎年100万ずつ10年にわたって銀行振り込みしました。しかしCさんの死後、結局贈与税を支払うことになりました。
よくあることですが、贈与の入金先とした子ども名義の口座をCさんが管理。子どもたちも贈与の具体的事実を把握していなかったため、税務調査で「名義預金」とみなされ、相続税が課せられてしまったのです。ならばどうすればよいのか。堅苦しいようですが「贈与契約書」をつくことです。そして氏名は必ず自筆にすること。子どもたちとの間の贈与契約が認められれば、相続税対象にはならずにすむのです。
生前贈与を考えるなら長期計画で暦年贈与するのが効果的ですが、ここにも注意点があります。
Cさんは1人毎年110万までの贈与は非課税という暦年贈与の仕組みを利用し、子どもたちに毎年100万ずつ10年にわたって銀行振り込みしました。しかしCさんの死後、結局贈与税を支払うことになりました。
よくあることですが、贈与の入金先とした子ども名義の口座をCさんが管理。子どもたちも贈与の具体的事実を把握していなかったため、税務調査で「名義預金」とみなされ、相続税が課せられてしまったのです。ならばどうすればよいのか。堅苦しいようですが「贈与契約書」をつくことです。そして氏名は必ず自筆にすること。子どもたちとの間の贈与契約が認められれば、相続税対象にはならずにすむのです。
06.被相続人(亡くなった人)の借金が財産より多い
返済できないくらいの額の連帯保証人になっている等
隠れ負債に気を付けろ! 3か月以内に財産放棄を
その場合、すべての相続を放棄する「相続放棄」が必須になります。相続放棄をするには、相続放棄申述書等の書類を用意し、家庭裁判所で手続きをする必要がありますが、被相続人が亡くなってから(相続人が相続の発生を知ってから)原則3か月が期限となっています。3か月以内に何の手続きもしないと、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する単純承認をしたとみなされます。 しかし、故人の預金通帳の凍結解除の手続きをしたり、故人の預金を引き出して生活費等に使用したり、故人の車を廃車・名義変更したりしていると、相続放棄はできなくなるので要注意! |
親が事業主として法人の連帯保証人となっている場合や、相続について親や親族と話をしたことがなく、負債について把握していない場合も要注意。遺品整理中に隠れ負債が見つかるなんていうケースもあります。本人に借金がなくても、知人の連帯保証人になっている場合も負の相続になるので気をつけましょう。
07.隠し子は相続人?
被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本をとる
なるべく早く被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を確認しておくべきですが、古い戸籍の場合、災害や戦争による滅失、また一時的に他の戸籍に移ったなどの理由により、出生から死亡までの戸籍がつながらない場合があります。 |
Yさんは高齢の父親が亡くなったあと、父親の出生から亡くなるまでの戸籍を取り寄せましたが、15歳から17歳の間の戸籍が見つからず、不動産相続を進めることができませんでした。15歳から17歳の間に子供をもうけていた可能性も否定できないと役所に言われたのです。まさかそんなはずはないと訴えましたが、決まりだからと認めてもらえず。その後の調べで、当時父親は実兄の戸籍に入っていたことがわかり、無事相続手続きは進みましたが、高齢の方の場合、出生から亡くなるまでの一連の戸籍をとるのは困難な場合もあります。元気なうちに被相続人のルーツについて聞いておくのも良いかもしれません。